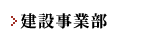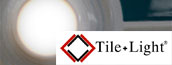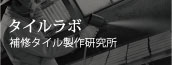製品の安全性を考えれば、工業製品がクリアしなければならないのは、規格です。
タイルの統一規格として、日本にはJISの陶磁器質タイル(JIS A 5209 2008)がありますが、それ以上に厳しく社内規格を設けることで優良な製品はできあがっていきます。
タイルを貼ったのち、割れや剥がれが起こってはたまりません。そこで、強度、吸水率、寸法・形状、ねじれや反りなどに明確な規格があり、工場内で建築物件ごとの製品単位で抜き取り検査を行っています。
寸法と形状と一言でいいますが、土を焼くという不安定な工程を経るやきものの特性を考えると、ミリ単位の均一な精度をあげる機械化と技術の進歩は驚愕的です。

写真は強度を検査しています。タイルの中央に荷重をかけたときの、タイルのスパン1㎝幅1㎝に換算したときの破壊荷重を計ります。
また、吸水率は低ければ低いほど良いのが、外壁や水回りに用いられるタイルの重要な機能です。
寒冷地では含んだ水が凍り、タイルの割れにつながりかねません。JIS規格は3%以下ですが、加納では1%の厳しいものにして製品向上を図っています。
こちらの検査はちょっとおもしろいです。タイルを2時間グツグツと煮沸して、12時間放置し、乾燥したものとの水分含有量を比較してだします。

これは赤外線水分計
成形前の坏土(=陶土原料)も水分量を赤外線水分計でも計ります。
これは、成形に適した水分量を知るもの。5%を切ると、焼成後にパイ生地のような層ができてしまうのです。
ばち(相対する辺の寸法差)などの寸法はノギスで測ります。
壁面に貼り付けるときタイル裏面の形状を「裏足」といいますが、剥離防止には重要な部分です。製品の大きさによって異なりますが、例えば45二丁(45㍉×95㍉)裏足の高さも0.7㍉以上と決められています。
形状や厚みに関わるほとんどの寸法は、JIS規格より誤差を厳しくしています。
社内で検査する以外にも、必要に応じて耐摩耗性や釉薬の耐薬品性などの検査は、同町内にある(財)全国タイル検査技術協会へ出しています。
このような安全な製品作りは「ものづくりの良心」だと思います。(Muto)